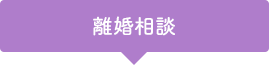Q. 懲戒処分の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
A. 懲戒処分とは、従業員が企業の規律やルールに違反した際に、その違反行為に対して企業が行う制裁措置のことです。企業は、従業員に対して規律を守らせるために、就業規則に基づき懲戒処分を行う権限を持っています。ここでは、懲戒処分の主な種類とそれぞれの特徴について解説します。
1. 懲戒処分の目的
懲戒処分は、従業員の規律違反や不正行為に対して適切な対応を取るためのものであり、企業内の秩序を維持し、他の従業員にも規律を守る意識を持たせる役割があります。懲戒処分を通じて、再発防止や職場の信頼関係の維持が図られます。
2. 懲戒処分の種類
懲戒処分にはさまざまな種類があり、違反の内容や程度に応じて処分の重さが変わります。一般的に、日本の企業でよく見られる懲戒処分は以下の通りです。
① 戒告
戒告は、懲戒処分の中で最も軽いものです。従業員に対して口頭または文書で注意を行い、今後同じ過ちを繰り返さないよう警告します。戒告は通常、規律違反が比較的軽微な場合に適用されます。
② 譴責(けんせき)
譴責は、戒告よりもやや重い処分であり、文書での厳重な注意が行われます。さらに、労働者に始末書の提出が求められます。
③ 減給
減給は、従業員の給与の一部を減額する懲戒処分です。労働基準法では、減給処分の上限として、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。
④ 出勤停止
出勤停止は、一定期間従業員に対して出勤を禁じ、その間の賃金を支払わない懲戒処分です。通常は1週間から10日間程度の出勤停止処分が多いです。従業員に対する影響は大きく、将来の昇進や昇給に悪影響を及ぼすこともあります。
⑤ 降格
降格は、従業員の役職や職位を引き下げる懲戒処分です。降格に伴って給与や待遇が下がることが一般的で、職場内での評価にも大きな影響を与えます。
⑥ 諭旨解雇
諭旨解雇は、会社が従業員に対して自主退職を促す形で行われる処分です。従業員に対して「退職を勧める」という形で処分を行い、従業員がそれに応じて退職する場合、解雇とは異なり、自主的な退職として扱われます。
⑦ 懲戒解雇
懲戒解雇は、最も重い懲戒処分であり、従業員を懲戒処分として解雇することをいいます。懲戒解雇は通常の解雇とは異なり、退職金の支払いが行われないか減額されることが多いです。
3. 懲戒処分の注意点
懲戒処分を行う際には、いくつかの有効要件があります。
・就業規則への記載
企業が懲戒処分を行うには、事前に就業規則に懲戒処分の内容を定めておくことが必要です。
・処分の相当性
懲戒事由に該当する行為があったとしても、処分が重すぎる場合には懲戒権の濫用となります。
まとめ
懲戒処分には戒告から懲戒解雇まで、さまざまな種類があり、違反行為の内容や程度に応じて適用されます。懲戒処分に関するトラブルでお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所にご相談ください。

(弁護士 山本祥大)