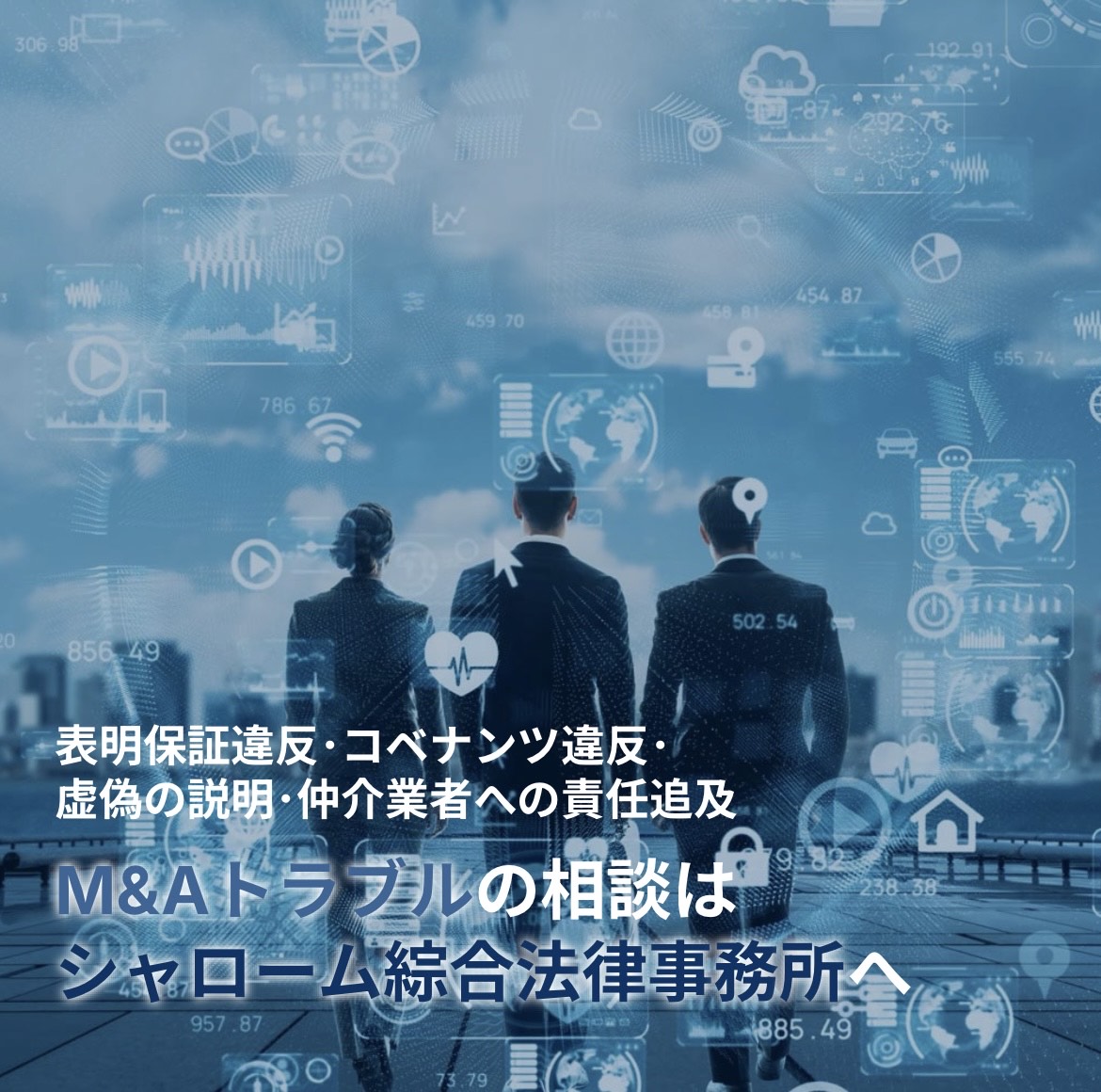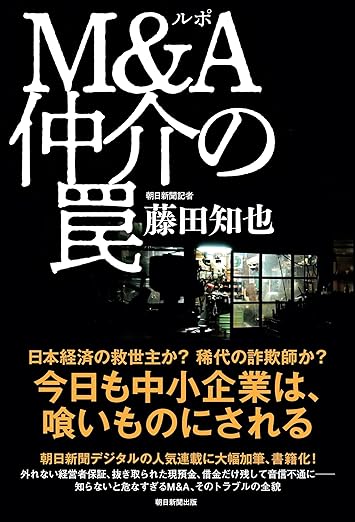2025/09/03
PEファンドが買主となるM&Aで起こりがちなトラブルと実務対応の勘所

我が国におけるM&A件数が増加する中で 、近年、投資ファンド(PEファンド)が買主となるM&Aが急増しています。当事務所でも、ファンドが絡んだM&Aトラブルのご相談が増加傾向にあります。
企業再編や事業承継の一環として、PEファンドが対象会社を取得するケースでは、譲渡対価の支払方法や業績連動型の契約構造が複雑化し、譲渡後に紛争が生じるリスクも高まります。この記事では、PEファンドが買主となるM&Aで実際に起こり得るトラブルと、それに対する実務的な対応策を解説します。
⚠️よくあるトラブル事例
1. アーンアウト条項を巡る紛争
譲渡対価の一部を、クロージング後の業績に連動させて支払う「アーンアウト」構造は、ファンド買収案件で頻出します。
📌典型的な争点:
• 業績評価の基準が曖昧で、売主側が「達成済み」と主張、ファンド側がこれを否認。
• 買収後の経営方針変更により、売主が「不当な操作」と反論。
• 会計処理やKPIの定義に齟齬があり、解釈が分かれる。
2. 表明保証違反と補償請求
ファンドが買主となる場合、対象会社の表明保証違反に基づく補償請求等が争点となります。
📌実務上の課題:
• 売主が「開示済み」として責任を否定。
• ファンド側が「重要な事実の不開示」として違反を主張。
• 損害額の算定が困難で、交渉が長期化。
3. クロージング後の情報取得と経営統制
買収後、ファンドが対象会社の経営に関与する場合、情報開示義務や経営判断の正当性が争点になることがあります。
⚙️実務対応のポイント
• 契約書での定義の明確化
アーンアウトの評価基準、KPI、会計方針は具体的に記載し、曖昧な表現を避ける。
• 表明保証の範囲と違反時の対応策
売主の開示義務と、ファンド側の情報取得体制を契約上で整理。
• 紛争解決条項の設計
仲裁条項や裁判管轄の選定が、紛争時の対応コストに直結する。

<Q&A>
Q1: PEファンドとは何ですか?
A:PEファンド(プライベート・エクイティ・ファンド)とは、未上場企業の株式に投資し、経営改善や成長支援を通じて企業価値を高め、数年後に売却(M&AやIPO)することで利益を得ることを目的とする投資ファンドです。企業の再編や事業承継の局面で活用されることが多く、経営ノウハウや人材を提供しながら、買収先企業の価値向上に積極的に関与します。
Q2: アーンアウトとは何ですか?
A: M&A契約で、譲渡対価の一部を対象企業の業績に連動させて支払う仕組みです。クロージング後の売上や利益などを基準に、追加支払額が決定されます。
Q3: 買主がファンドの場合、表明保証違反を売主に追及することは可能ですか?
A: 契約内容と表明保証の範囲によって異なります。売主が「開示済み」と主張するケースもありますが、重要な事実の不開示があれば、責任追及の余地があります。
Q4: 業績未達成を理由にファンドによる支払拒否は認められますか?
A: 契約上の評価基準と、実際の経営状況によって判断されます。売主側が「達成済み」と主張する場合、経営方針の変更や操作があったかどうかが争点になり得ます。
Q5: KPIとは何ですか?M&A契約でどう使われますか?
A: KPI(Key Performance Indicator)は「重要業績評価指標」のことで、企業の業績を定量的に測るための指標です。M&A契約では、アーンアウト条項の支払条件として設定されることが多く、売上高・EBITDA・新規契約件数などがKPIとして使われます。契約書でKPIの定義が曖昧だと、譲渡後に紛争が生じるリスクがあります。
📣まとめ:
専門的な視点での早期相談が鍵!
ファンドが買主となるM&Aでは、契約構造が複雑で、譲渡後の紛争リスクも高くなります。実務に精通した弁護士による事前の契約書チェックと、トラブル発生時の迅速な対応が不可欠です。
📩ご相談はこちらから
PEファンドが買主となるM&Aの契約構造や譲渡後の紛争にお悩みの方は、シャローム綜合法律事務所へご相談ください。 実務に精通した弁護士が、契約段階から紛争対応まで一貫してサポートします。まずはネット予約をご利用ください。遠方のご相談者様の場合は、オンライン相談も対応可能です。
詳しくは、バナーをクリック!
【弁護士紹介】

中川内峰幸(なかがわち みねゆき)
・M&Aトラブル対応実績多数。
・表明保証違反やM&A仲介会社との紛争に精通。
・企業内弁護士として多数のM&A案件に携わる。現在は、シャローム綜合法律事務所の代表弁護士。
・金融機関や中小企業からの相談多数。
・M&Aトラブルに関し、朝日新聞、週刊東洋経済、ニッキン、テレビ大阪等メディア掲載実績多数。