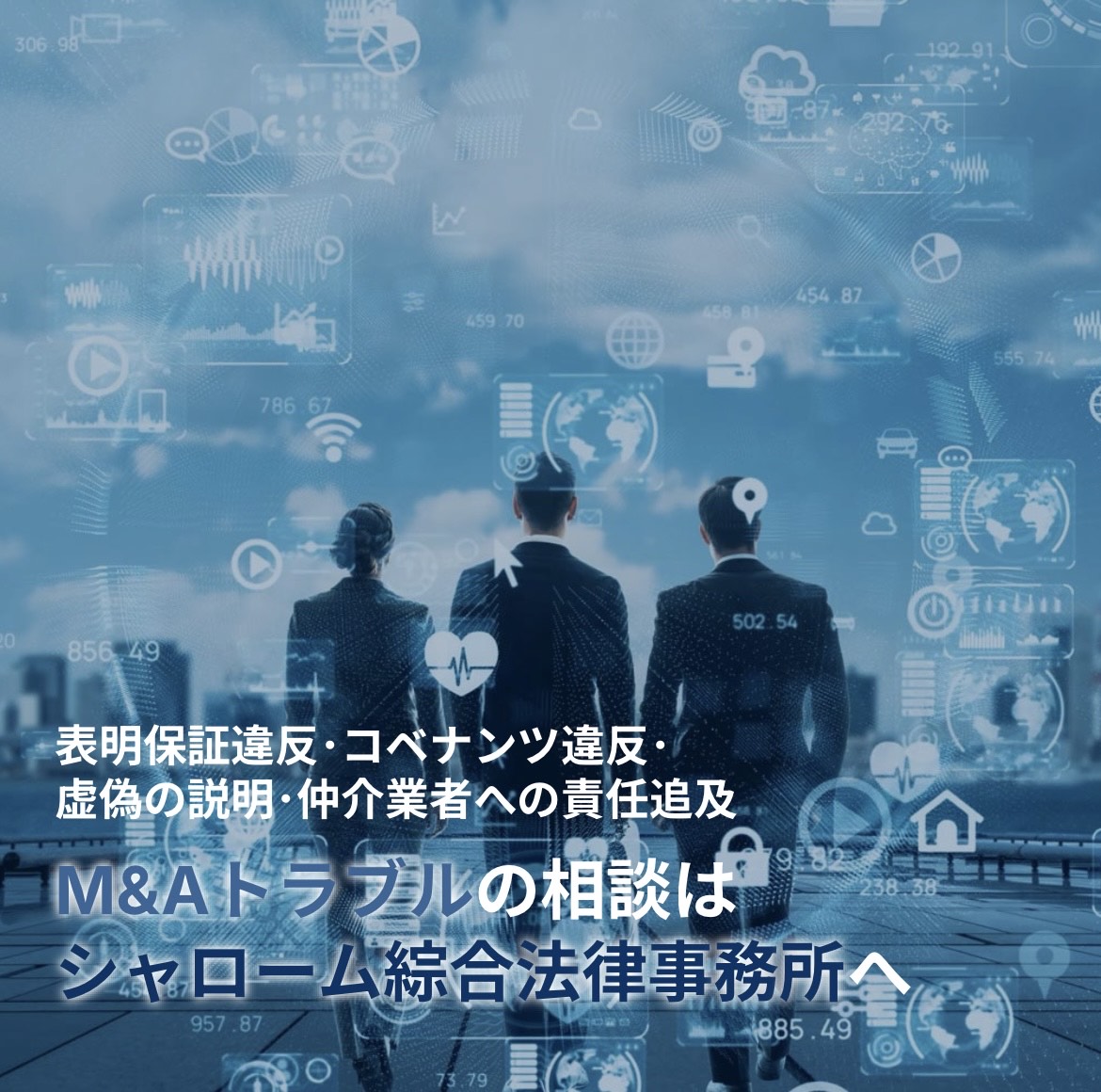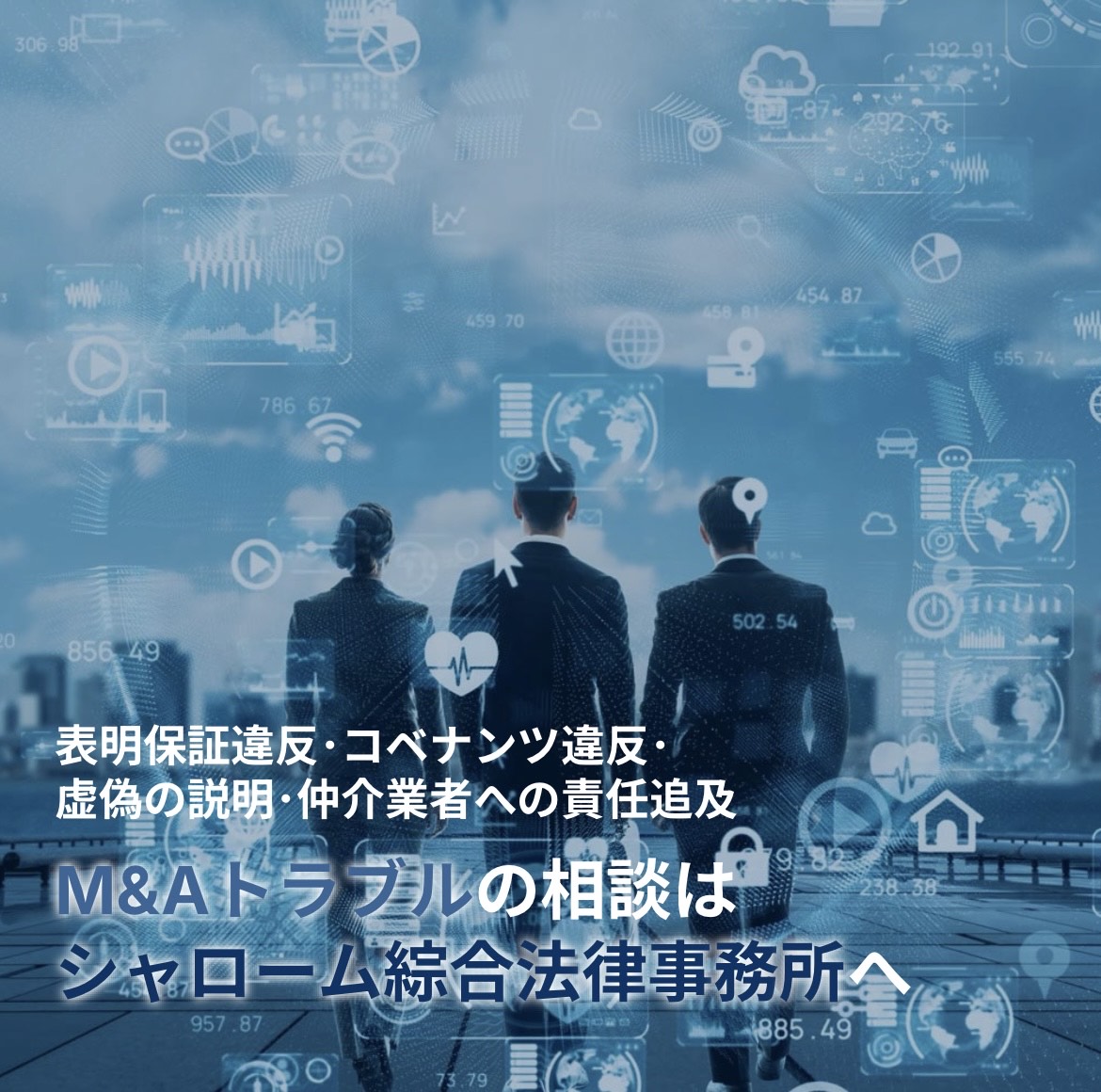
中小のM&Aにおいて、悪質な買主(買収した企業の資金を抜き取って失踪したり、契約に反して経営者保証の解除に応じないなど)について昨今問題視されていますが、多少違和感を覚える風潮です。というのは、詐欺的な手法を用いるのは何も買主に限られる話ではありません。悪質な売主も存在するのです。
最近ご相談が多いのは、YouTubeチャンネルの売買。事業譲渡ですね。株式譲渡のみならず、事業譲渡もM&Aです。
これが結構な高額で取引されておりまして、その多くはM&Aのマッチングサイト(プラットフォーム)を利用していることが特色です。つまり、個人間で売り買いがなされ、その間に助言を行うような第三者を介さない取引形態です。多くの場合、利用者は取引が成約した場合にプラットフォームに費用を払います。
騙されるのは買主の方で、開設して間もないYouTubeチャンネルにも関わらず、「月30万円の収益が出ています」「台本、編集等の知識がない方でも簡単に運営できます」「ネタが豊富で高単価なジャンルです」「属人性なしなのでフル外注が可能です」などの謳い文句に誘引されて取引に入ります。譲渡理由につき、「別事業に注力するため、スピード重視でお願いします」などという内容が掲載されていることも多いですね。
このようなYouTubeチャンネルが売りに出されていて、数十万円、あるいは数百万円で買うわけです。しかし購入後、当初売主から聞かされていたような収益が出ないことが判明して、買主はおかしいと感じることになります。このようなご相談は、最近ものすごく増えてきています。
契約書を見てみると、実に杜撰な内容でして、それもそのはず、マッチングサイトが用意している雛形を当事者同士が、内容を多少いじって利用していると。もちろんDDも行っていませんし、弁護士などの専門家も入っていません。こうなると、後になって紛争を解決するのにもなかなか厄介な状態です。
これらの全てが詐欺的案件だとはいいません。真っ当な売主が、真っ当なチャンネルを譲渡した結果、買主側の運営手法に問題があり収益が発生しないケースもあるでしょう。しかし、開設して数か月しか経っていないにも関わらず、一定の収益があると謳い、これを急いで譲渡するという共通項があり、こういった類のトラブルが非常に目立つようになっているのは確かです。もちろん、買主の側にも落ち度はあります。本当に信用できる案件であるのか、もっと詳細に調査する必要があったといえます。彼ら(彼女ら)を見ていますと、どうやら、フリマアプリで「モノ」を売り買いするのと似たような感覚で「事業」を売買しているようにも思えます。しかし事業譲渡もれっきとしたM&Aであり、M&Aはそんなに簡単なものではありません。
何でもフリマアプリで売り買いできる時代のようですが、M&Aプラットフォームの運営会社は、このようなトラブルが発生していることをどのように捉えているのでしょうか? そもそも、株式や事業をプラットフォームで売買すること自体の是非も問われるのではないでしょうか?
悪質な売主は、別にYouTubeチャンネルの売主に限りません。売買行為が行われる以上、そこに詐欺的な手法を用いる輩が発生することは全く不思議なことではありません。それが土地であれ、株式であれ、YouTubeチャンネルであれです。ただし、不動産や法人の譲渡と比べて規模が小さく、また譲渡後の運用・運営も楽に見えることから、副業感覚でさほど深く検討することなく購入に走る買主が多いのかもしれません。こうなるとM&Aトラブルというよりは、消費者問題といった方が適当かもしれません。
さて、以上述べましたとおり、問題があるのは何も買主だけでなく、売主においても同じなのです。そして売主も買主も、自らが契約の当事者となるのですから、不測の損害を被らないよう、当事者意識をもって自衛しなければなりません。安易に儲け話に乗るのではなく、慎重に慎重を重ねて検討すること。そして自分だけでは分からない場合には、弁護士などの専門家の意見を聞くこと。それが重要です。騙された方にとっては実に厳しい言い方となってしまいますが、そのような自衛を怠ったことによるトラブル発生の場合には、「泣き寝入り」ではなく「自業自得」と言われてしまっても仕方がないのかもしれません。
また、上記M&Aプラットフォームの運営会社も、今後何らかの対策を立てる必要があると考えます。
(弁護士 中川内 峰幸)