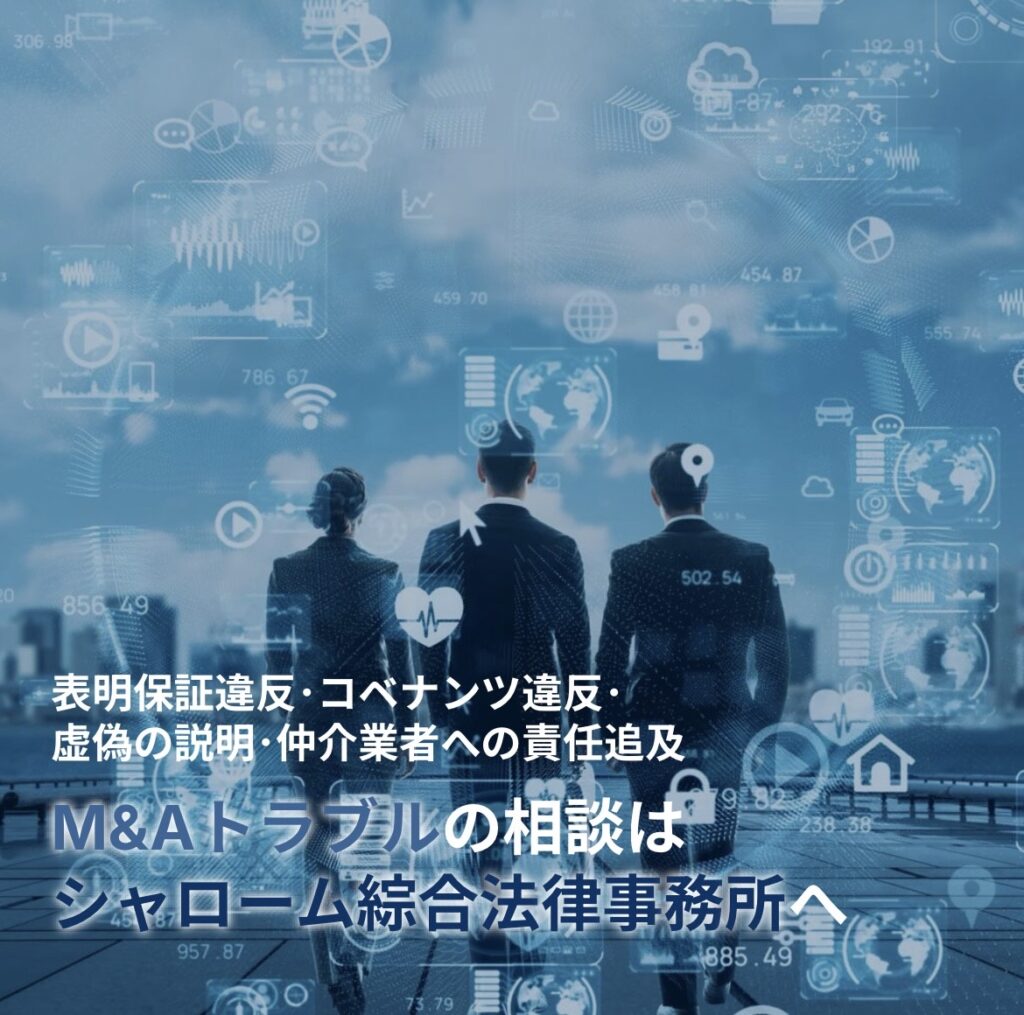M&A仲介トラブル・詐欺──仲介会社との紛争が裁判に発展するケース
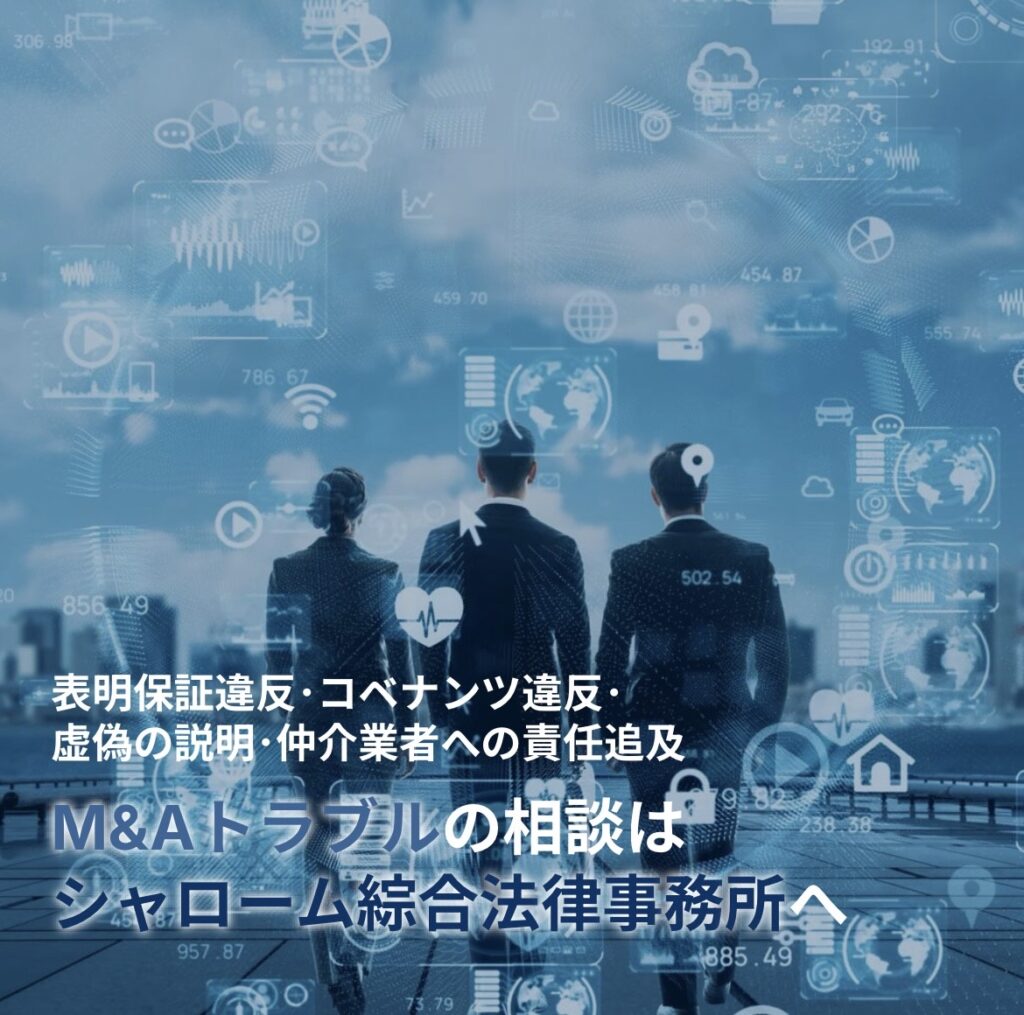
M&Aは専門的な知識が必要なため、多くの経営者が仲介会社に依頼します。
しかし、仲介会社との間で「説明不足」「誤誘導」「過大な手数料請求」などのトラブルが発生し、裁判に発展するケースも少なくありません。
よくあるご相談事例
・ 仲介会社が成約を急がせるばかりで、契約内容を熟考する暇もなく契約してしまった
・ 仲介会社に提示された譲渡価額が本当に適正なのかわからない
・ リーガルチェックを弁護士に依頼しようとしたら「この規模のM&Aでリーガルチェックは見たことがない」と言われた
・ デューデリジェンス(DD)が簡易的で、後から聞いていた話と違う点が次々と発覚
・ 仲介会社に確認しても「両手取引なので一方に有利なことは言えない」と回答された
・ 仲介会社が作成した契約書が杜撰で、M&A後に大きな損害を被った
・ 悪質な買い手を紹介されて大損害を受けたが、仲介会社は責任を持たずに逃げた
・ クロージング後に問題が判明して契約解除となったにもかかわらず、高額の仲介手数料だけは徴収された
・ 仲介手数料を支払えないキャッシュ状況なのに、対象会社に借入をさせてそこから支払うよう打診された
・ 仲介会社の段取りが悪く契約が破談となったが、着手金を返さない
・ 仲介契約上、損害賠償額の上限が設定されていて十分な補償が受けられない
・ 仲介会社が買い手の財務状況を調べないまま手続きが進み、経営者保証トラブルに発展
・ 仲介会社が情報漏洩をしているようだ
・ 経営者保証の承継のため、事前に金融機関へ接触しようとしたら、仲介会社に止められた
👉 今すぐご相談はこちら
実務上の影響
・ 成約を急がされた結果
→ 契約内容を十分に検討できず、後から重大な不利益条項が発覚し、数千万円規模の損害。
・ 譲渡価額の不適正
→ 仲介会社の提示額が市場価値より大幅に低く、売主が数億円単位で損失を被る。
・ リーガルチェックを妨害
→ 弁護士による契約書審査を拒まれ、杜撰な契約書でクロージング。後に訴訟へ発展。
・ 簡易DDの結果
→ デューデリジェンスが不十分で、買収後に隠れ債務や不利な契約が次々と発覚。
・ 両手取引による利益相反
→ 仲介会社が、優良顧客となる買主(ストロングバイヤー)の肩をもったため、売主が大損害。
・ 契約解除後の高額手数料請求
→ クロージング後に問題が判明して契約解除となったにもかかわらず、仲介会社が成功報酬だけは徴収。
・ 悪質な買い手の紹介
→ 財務状況を調査せずに買い手を紹介し、経営者保証トラブルや倒産に直結。
・ 情報漏洩
→ 仲介会社の杜撰な管理で機密情報が流出し、信用失墜や取引先離脱につながる。
・ 金融機関対応の妨害
→ 経営者保証の承継交渉を仲介会社に止められ、保証債務が残り経営者が個人資産を失う。
👉 今すぐご相談はこちら
解決の糸口
・ 仲介契約の条項を精査
・ 中小企業庁「中小M&Aガイドライン」への抵触を確認し、仲介会社の行為が公的指針に反していないかをチェック
・ 一般社団法人M&A支援機関協会(旧M&A仲介協会)の自主規制ルール(倫理規程・広告営業規程・コンプライアンス規程・契約重要事項説明規程)への違反を確認し、業界標準に照らして仲介会社の責任を追及
・ 仲介会社の故意又は重大な過失を根拠に、損害賠償請求
・ 裁判・交渉を通じて、適正な補償を獲得
👉 今すぐご相談はこちら
お早めにご相談ください!
M&A仲介会社とのトラブルは、そもそも仲介会社選定のミスが原因である場合が少なくありません。
M&A仲介を行う上で免許や資格は不要ですので、能力が不足している仲介会社が存在している事実は否定できません。
選んだ仲介会社の業務によってM&Aの問題が発生し、契約相手との間で大きな争いになることもあれば、「仲介詐欺」として仲介会社に責任を問う事態になることもありえます。
「M&A仲介トラブル」「M&A仲介詐欺」「M&A訴訟」でお困りの方は、ぜひ早めにご相談ください。
仲介会社への責任追及にも、契約上ほとんどの場合で期間制限があります。
弁護士が状況に合わせた対応策をご提案します。
👉 今すぐご相談はこちら
【弁護士紹介】中川内 峰幸(なかがわち みねゆき)

・M&Aトラブル対応実績多数。
・表明保証違反やM&A仲介会社との紛争に精通。
・企業内弁護士として多数のM&A案件に携わる。現在はシャローム綜合法律事務所の代表弁護士。
・金融機関や中小企業からの相談多数。
・M&Aトラブルに関し、朝日新聞、週刊東洋経済、ニッキン、テレビ大阪、中日新聞等メディア掲載実績多数。
M&Aトラブルについてより詳細な情報をお求めの方は、下のバナーをクリック!